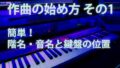いきなりですが、作曲をはじめるのに年齢は関係ないです。
特別な才能も楽器演奏の経験も不要です。
ただし、気をつけておきたいこともあります。
この記事では、
- 「作曲に年齢は関係ない」といえる理由
- 40代が気をつけたいこと
- まったく初心者の方の作曲の始め方
- 挫折せず、作曲スキルを楽しく身につける方法
年齢:40代半ば
音楽経験:20歳から10数年、ギター・バンド活動
音楽の実績:なし(インディーズのコンピレーションアルバムに参加した事がある程度)
作曲をはじめた年齢:本格的な作曲・DTMは40歳を超えてから
今の活動形態:曲・動画を作って動画サイトで公開
目次
作曲に年齢は関係ない!と言える理由

結論から言うと、作曲できるようになるために必要なのは
- 学び、上達する楽しさを実感すること
- 「出来るようになる!」という気持ち
特別な才能も楽器演奏の経験も不要です。
世の中には音楽講師がたくさんいますが、みんな口裏を合わせたかのように

「たくさんの生徒に教えて来たけど、始めるのに年齢は関係ない」
と、同じことを言っています。
これは「お客さん(=生徒)がたくさん欲しいから」という理由で言っているわけではなく、実際に年齢は関係ないからです。
若かろうが40代だろうが、やる事・学ぶ事は同じです。
「何々が加齢で衰えているから作曲できない・難しい」なんて事はないです。
脳の学習能力(新しい事を学んで身につける)は、知識と経験によって生涯向上し続けるといわれています。
また、新しい情報を理解する能力については、50歳がピークで、それまで伸び続けるといわれています。
(参考:アデコ株式会社 加齢と脳機能の衰えは無関係?知能は経験の積み重ねで向上する)
つまり能力の面では、若者より40代の方が有利です。
40代が作曲をはじめる際に気をつけたいこと(メリット・デメリット)
- 若い頃より集中力が落ちている
- 若い方が「誰かに認められたい」という欲求が強い
- 歳をとると、ちょっと触れただけで先が見えたような気になり、「自分にはダメそう」とか思ってしまいがち
- 若者よりたくさんの音楽に触れている
- 若い頃より物事を理解できる
- 若い頃より経済面で有利
たしかに若い頃と比べると、気力・体力の面で衰えを実感している方も多いと思います。
でも代わりに、状況を把握して「なるほどそういうことね」と理解する力は、人生経験が長い40代の方が有利です。
作曲に限らず「誰かに認められたい」という欲求は、男性にとって「モテたい」の次くらいに大きな原動力ですよね。
この点だけは、若者の方が有利です。
気力・体力・気持ちの面で若者に劣る点は、大人の知識・経験・理解力によってスムーズに上達していく事でカバーするように気をつけましょう。
(あ、もちろん、作曲して他人に聞いてもらえるようになると、モテます!)
40代の作曲の始め方

PC・スマホ・タブレットを使って作曲することを、日本ではDTM(デスクトップミュージック)と言います。
まずは、DTMに必要なモノを準備する必要があります。
楽器を使わない場合は、無料で揃えられます。
最低限必要なモノ(無料でOK)
- PCまたはスマホ・タブレット
- DAW
- オーディオインターフェイス(楽器を使う場合のみ)
- マイク(歌声・PCと直接接続できない楽器を録音する場合のみ)
- 歌声合成ソフト(ボカロ曲を作りたい場合のみ)
1:PCまたはスマホ

PCがなくても、スマホかタブレットがあれば出来ます。
ただし、作業効率(入力する労力や視認性)はPCの方が圧倒的に上です。
また、PCもスマホ・タブレットもハイスペックな方が快適ですが、低スペックでも問題ありません。
2:DAW

データ入力・録音・ミキシングなど、作曲全般の作業をするためのソフトをDAWといいます。
たくさん発売されているのですが、↓のDAWが定番です。
- Cakewalk(オールマイティ。無料。WINDOWSのみ)←おすすめ
- CUBASE(オールマイティ。有料。WINDOWS・Mac)
- Logic Pro(オールマイティ。有料。Macのみ)
- FL Studio(ダンスミュージック・ヒップホップに特化。有料。WINDOWS・Mac)←おすすめ
- Steinberg Cubasis(オールマイティ。有料。Android・iOS・Chrome OS)
- Auria Pro(オールマイティ。有料。iOSのみ)
- GarageBand(オールマイティ。無料。iOSのみ)←おすすめ
- FL Studio Mobile HD(ダンスミュージック・ヒップホップに特化。有料。Android・iOS)
Cakewalk
「続くかわからないから、とりあえず無料で」という方には、Cakewalkがおすすめです。
無料といっても、高価な有料ソフトと同等で、「なんでコレが無料なの!?」というレベルです。
「打ち込みだけで作曲」「楽器を使って作曲」「ボーカル・楽器を録音」など、オールマイティに対応できます。
Cubase
「俺はダンスミュージック・ヒップホップだけを全力でやるんだ!」という事でなければ、Cubaseがおすすめです。
Cubaseは、日本では圧倒的なシェアを誇っていて、「打ち込みだけで作曲」「楽器を使って作曲」「ボーカル・楽器を録音」など、オールマイティに対応できます。
(もちろん、ダンスミュージック・ヒップホップも作れます)
また、動画サイトなどでプロが公開している情報も、「Cubaseで何々をする方法」みたいなものが多いです。
そのため情報を得やすい(=スムーズに疑問を解決できる)というメリットもあります。
※初めての方は『通常版』の購入が必要です。
※『アップグレード版』『クロスグレード版』は、旧版・下位版を購入済みの方向けです。
Logic Pro
「Macのド定番ソフトで作業したい」という方には、Logic Proがおすすめです。
上記2つと同様に「打ち込みだけで作曲」「楽器を使って作曲」「ボーカルを録音」など、オールマイティに対応できて、ネットでの情報も多いです。
FL Studio
「俺はダンスミュージック・ヒップホップだけを全力でやるんだ!!」という方には、FL Studioがおすすめです。
ダンスミュージック・ヒップホップが作りやすい操作性になっています。
また、ダンスミュージック・ヒップホップシーンのトップアーティスト達が公開している情報も「FL Studioで何々する方法」みたいなのが多いので、疑問をスムーズに解決できます。
さらに、一度購入すれば、永久に無料でアップデートできるというのも大きな魅力です。
多くのDAWは1~2年に1回、大型アップデートがあります。
アップデートしたい場合は、その度に通常購入または割引価格での購入が必要になります。
でもFL STUDIOなら、一度購入するだけで永久に最新版を使えます。
※機能が違う複数のグレードがありますが、『プロディーサーエディション』が人気です。
Steinberg Cubasis
Cubaseのモバイル版で、どんな音楽にも使えます。
Auria Pro
こちらもどんな音楽にも使えますが、iOS専用です。
GarageBand
iOS専用ですが、iPhone・iPadをお使いなら、まずはGarageBandから始められるのをおすすめします。
たとえば「歌メロを思いついたけど、楽器のことはぜんぜんわからない」というような場合でも、GarageBandなら最初から用意されている伴奏パターンを使って並べるだけで、手軽に形にできます。
楽しく続けるためには「形にする」がすごく大切なので、手軽に形にできるメリットは大きいです。
(他のDAWでも同様のことができますが、GarageBandほどはお手軽ではないです)
FL Studio Mobile HD
FL Studioのモバイル版で、「俺はダンスミュージック・ヒップホップだけを全力でやるんだ!!」という方にぴったりです。
3:オーディオインターフェイス(ボーカル・楽器の録音をする場合のみ)

エレキギターやマイク等を接続して録音するためには、オーディオインターフェイスという、PCと接続するための機器が必要になります。
ピンキリなのですが、
- MOTU M2(値段は高いけど、ハイエンドモデルに匹敵する音質で、動画配信に便利な機能も備える)
- STEINBERG UR22C(Cubase AIが付属するからお得。動画配信に便利な機能も備える)←おすすめ
- BEHRINGER UM2(値段が安い)
Cubaseにはいくつかのグレードがあって、STEINBERG UR22に付属するCubase AIというのは下位グレードです。
下位とはいっても、最初のうちは十分すぎるくらいの機能・内容です。
また、高いグレードが欲しくなったら、安価でアップグレードもできます。
そのため、もしDAWはCubaseを選ばれるなら、STEINBERG UR22C+付属のCubase AIで始められるのをおすすめします。
4:マイク(ボーカル・直接接続できない楽器を録音する場合のみ)

ボーカルやピアノ・アコギ・フルート・バイオリンなど、PCに直接接続できない楽器を録音するためには、オーディオインターフェイスとマイクが必要になります。
マイクは性能・価格の幅がかなり広いですが、
- SHURE SM57(楽器もボーカルもイケる)
- SHURE SM58(ボーカルに特化)
マイクは価格と音質がかなり比例する(安かろう悪かろう)ので、もしマイクも購入されるなら、妥協せず選んだ方が長い目で見るとお得です。
5:歌声合成ソフト(ボカロ曲を作りたい場合のみ)

いわゆる”ボカロ曲”を作りたい場合は、歌声合成ソフトが必要になります。
選択肢はたくさんあるのですが、
- 初音ミク V4X(ド定番だけど、最近は古いモノ扱いされがち)
- Cevio AI(可不などが有名。WINDOWSのみ)
- VoiSona(Cevioの姉妹ブランド。無料でも始められる)
- Synthesizer V(重音テトなどが有名。機能制限つきの無料版もあり)
「どうしてもこのキャラじゃなきゃ!!」というこだわりがなければ、Cevio AIが無難です。
環境を整えたら、後は学びながら実践していくだけですが、動画講座の活用がおすすめ

環境を整えるまでの話が長くなってしまいましたが……。
環境さえ整えたら、あとは実践しながら学んでいくだけです。
実践しながら学ぶといっても、

「何から?どこから?まったくわかんないんだけど……?」
となってしまいますよね。
作曲するには
- DAWの使い方
- DAW内で使う音源・プラグインの使い方
- メロディーのこと
- リズムのこと
- コードのこと
- いろんな楽器・音色のこと
また、他人の曲を聞いて「何をやっているか?何が起きているか?」を聞き取る力を養うことも必要です。
始める前は

「うへぇ、大変そう」
とか

「難しそう……」
と感じるかもしれませんが、実際やってみると、ぜんぜん大したことないです。
挫折せず、効率よく楽しく身につけるなら動画講座
ぜんんぜんたいした事ないとはいえ、挫折せず、効率よく楽しく身につけるには
- 少しでも早い段階から、楽しさを実感する
- わからない事をスムーズに解決する
- 少しでも早く完成させる
どれかが欠けると、楽しさを感じられなくて続かないです。
身につけていくには、
- 有料の動画講座を活用
- 講師によるオンラインレッスンを活用
- 書籍を活用
- 無料で公開されているネットの情報を活用
1:有料の動画講座
- 特になし(費用がかかる)
- オンラインレッスンよりはだいぶ安い
- ゼロから最後まで、体系的に学べる
- わからないことは質問できる
- いつでもどこでも何度でも、自分のペースで視聴・学習できる
費用面の折り合いがつくなら、有料の動画講座を活用するのが一番いいです。
動画講座は、オンラインレッスン(作曲講師がリアルタイムで教えてくれる)を、個人で視聴・学習するのに最適化したような形式です。
自分の都合・ペースに合わせていつでも何度でも観れるのが強みです。
動画なので、書籍と違って
- 実際に操作している画面
- どのような結果(音)になるか
その結果、他の方法よりも効率よく身に付き、早い段階で楽しさを実感できるから、楽しい気分でどんどん上達できます。
また、オンラインレッスンみたいにその場で質問することはできませんが、質問できるサポート掲示板などが用意されている事が多いです。
動画講座を提供しているサービスはたくさんありますが、音楽関係が充実しているサービスはかなり少ないです。
その中で、世界最大級の動画講座サービス『Udemy』は、音楽関係もかなり充実していておすすめです。
「必要な情報・欲しい情報がすべて手に入る」と言っても過言ではないくらい充実しています。
2:講師によるオンラインレッスン
- 時間に縛られる
- 高額
- 体系的に学べる
- 疑問をその場で解決できる
作曲講師がマンツーマンや1対少人数で教えてくれます。
「何日の何時から」と時間に縛られたり、「うわぁ、前回から何一つ進めてない……なのにレッスン料は払わないといけない……」となったりするのがデメリットです。
時間と経済面に余裕があれば、良い選択です。
個人的には「音楽は人に手取り足取り教えてもらうもんじゃないでしょ、自分でモノするのがカッコイイ」と思っています。
3:書籍
- 読んだだけでわかった気になりがち
- 有料の動画と比べたら安い
- 体系的に学べる
- 自分に合ったモノを選べる
安く体系的に学べるのは、大きなメリットです。
「とっつきやすいけど浅すぎる」や「とっつきにくいけど必要な事が網羅されてる」「書いてあることに沿って進めていけば完成させられる」「ボカロ曲を作りたい」などなど、性格・目的に合わせて選べるのもメリットです。
ただし気をつけておきたいのが、書籍だと「読んだだけで(頭の中だけで)わかった気になってしまいがち」なことです。
音楽は、実際に音を聞き、そして自分でも実際に音を出しながらやらないと、身につきません。
かならず「読む」⇒「自分でも音を出してみる」で進めていきましょう。
4:無料で公開されているネットの情報
- 体系的に学びにくい
- 効率が悪すぎる
- 費用がかからない
- 情報発信者に質問できる場合もある
ネットには、人気アーティスト・作曲家による「○○で○○する方法」みたいなチュートリアル動画・記事があたくさんあります。
そのため、欲しい情報がハッキリしている場合は、ピンポイントで学べます。
その反面、ゼロから最後までを体系的に学べる動画・記事はほとんどないです。
なので、「○○がわからないから検索……コレは違うな……やっと情報が見つかったけど、説明に使われてる△△の意味がわからない……△△で検索……」となってしまい、まったくの初心者がゼロから学ぶ場合は、かなり効率が悪いです。
スムーズに学べないと、上達・形にするのが難しくなり、投げ出す要因になります。
この記事のまとめ
- 作曲に必要なのは「学び、上達する楽しさを実感すること」「出来るようになる!という気持ち」だけ(特別な才能・楽器演奏の経験は不要)
- 脳の学習能力は、知識と経験によって生涯向上し続ける(=若者より有利)
- 気力・体力・「誰かに認められたい」という気持ちの面では、若者に劣る
- 若者に劣る点は、大人の知識・経験・理解力によってスムーズに上達していく事でカバーする
- 作りたい音楽のジャンルに合わせて、必要な環境をそろえる(PCまたはスマホ・DAW・オーディオインターフェイス・マイク・歌声合成ソフト)
- 環境が揃ったら、ネットに無料で公開されている情報・書籍・オンラインレッスン・動画講座などで学びながら実践していく
- ネットに無料公開されている情報や書籍より、有料の動画講座がおすすめ(効率よく身に付くから、早い段階から楽しさを実感できて、どんどん上達できるので)
【Udemy(ユーデミー)】
作曲以外の趣味については↓の記事でくわしくご紹介しているので、ぜひそちらも参考にしてみてくださいね。