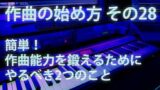この記事では、耳コピできるようになるための基礎をご紹介しますね。
ただ、いきなりこんな事を書くとすごく萎えると思いますが……。
耳コピは作曲能力UPのために必須のスキルですが、一朝一夕ですぐ出来るようになる魔法はありません。
つまり、地道なトレーニングが必要です。
でも地道にトレーニングすれば、

「コードもメロディーもぜんぜんわからない……」
という段階からちゃんと抜け出せます。
あきらめずにスキルを磨きましょう。
目次
耳コピのやり方

0:ネットで情報収集
ネットで検索すると、コード進行・BPM・キーなどの情報が手に入る場合があります。
最初のうちはネットで情報を集めてから始めた方が、挫折を防げます。
1:音色を似せる
まず、コピーしたい音色と似た音色を用意します。
ピアノならピアノ、アコギならアコギ、シンセのSUPER SAWならSUPER SAWなど。
歪んだギターやシンセなどは、歪み具合も可能な限り似せましょう。
音色が違うと、慣れないうちは合っているのかどうか判断が難しくなります。
2:ベースを聞いてルートを探る
おそらく、ここが最難関です。
だって、ベースがよく聞こえないことって、すごく多いですよね……。
まずは、ベースを1オクターブ(=半音12個)何度も順番に弾き、ベースの音を耳に馴染ませます。
次に、ベース(楽器・音色)、あるいはピアノ・ギター等を聞いて、ルートを探ります。
DAWで
- センターの音だけ残して、左右の音をカット
- EQで高音をカット
ただし、ベースが常にルートを弾いているとは限りません。
ルートを弾いているっぽい個所(他より低音の箇所)を見つけましょう。
また、ピアノ・ギターなどはルートを省略していることも多いので要注意です。
1オクターブ=半音12個なので、12個試せば当たります。
補足:ツールに頼るのもアリ
DTMが発達している今は、自力での耳コピにこだわる必要は少なくなって来ています。
たとえばZplane社の『deCoda』というプラグインは、数秒でコード・メロディ・曲構成を可視化してれくます。
楽天市場⇒ZPLANE/DECODA【オンライン納品】【在庫あり】
deCodaには劣りますが、それなりに高性能な『DamRsn NeuralNote』という無料プラグインもあります。
耳を鍛えていくのは、作曲者として必須です。
でもコピー段階でつまづいていると、いつまで経っても作曲能力が上がりません。
耳コピサポートツールも上手に活用していきましょう。
3:メジャー・マイナーを聞き分ける
ルートがわかったら、次は「コードがメジャーっぽいか?マイナーっぽいか?」を聞きます。
普段から
- メジャーコード
- マイナーコード
- (VIIm-5のような)-5のコード
↓の音源は、C・Cm・Cm-5を順番に鳴らした例です。
メジャーともマイナーともちょっと違うとき
「Cメジャーっぽいけどちょっと違うなぁ」というような場合は、
- まずは7thコード
- 次に△7thコード
- その他のテンションコードやsus4など
この辺も慣れなので、普段から耳に馴染ませておきましょう。
アコギの場合
アコギのローコードの場合、ボイシングの都合で、各コードが独特の聞こえ方をします。
そのため、ローコードの音を耳に馴染ませておくと早いです。
4:ベースとコードを聞いているうちに、キーとスケールが見えて来る
ベース・コードをいくつかコピーできたら、なんとなく「キーが何で、何々スケールかな?」というのが予測できます。
予測できたら、予測したキー・スケールに沿ってダイアトニックコードを試します。
ダイアトニックコードでしっくり来ない場合は、借用和音・一時転調を試します。
(「どんな借用和音・一時転調が使われるか?」も、コピーしているうちに予測できます)
5:メロディーを聞く
ここまで来たら、キー・スケールが予測できた状態です。
予測したキー・スケールに沿って、メロディーを一音ずつ拾っていきます。
次の記事では、作曲能力を鍛える方法をご紹介しますね。
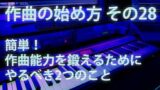
この記事のまとめ
耳コピは、いきなり出来るものではありません。
また、一朝一夕でできるようになる魔法もありません。
地道なトレーニングとコピー作業を繰り返すしか方法はありません。
とはいえ、DTMが発達した今は、自力での耳コピにこだわる必要は少なくなって来ています。
たとえばZplane社の『deCoda』というプラグインは、数秒でコード・メロディ・曲構成を可視化してれくます。
楽天市場⇒ZPLANE/DECODA【オンライン納品】【在庫あり】
deCodaには劣りますが、それなりに高性能な『DamRsn NeuralNote』という無料プラグインもあります。
耳を鍛えていくのは、作曲者として必須です。
でもコピー段階でつまづいていると、いつまで経っても作曲能力が上がりませんし、作曲の楽しさも体験できません。
(つまづきながら試行錯誤する体験も大切ではありますが……)
耳コピサポートツールも上手に活用していきましょう。
次の記事では、作曲能力を鍛える方法をご紹介しますね。