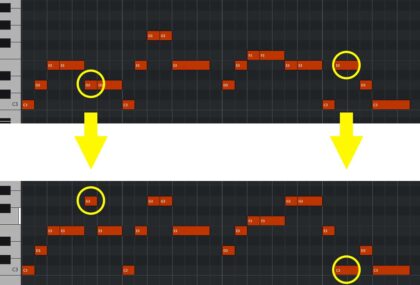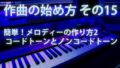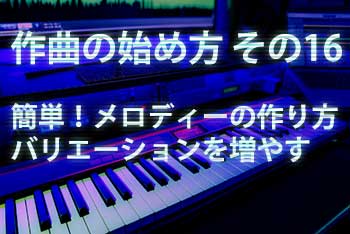
この記事では、メロディーの作り方のバリエーションを増やす方法を解説しますね。
メロディーの作り方のバリエーション

これまでの記事では↑の画像のように、”短いフレーズを4回繰り返す”という基本に沿って、「たたたたーた」というフレーズを繰り返してきました。
他のバリエーションも身につけると、多彩なメロディーを作れるようになります。
バリエーション1:2パターンを組み合わせる
短いフレーズを2種類作って、フレーズ1+フレーズ2を繰り返すパターンです。
(コードはF⇒C⇒G⇒Cです)以前の記事でご紹介したように、
- 単純に繰り返すのではなく、前半・後半でのコール&レスポンスを意識する
- 最後は”一段落した感”を出すために、rootで終わる
(以前の解説記事はこちら⇒コール&レスポンスを意識する)
上記の例でいうと、2小節目に対して、4小節目はリズムを少しだけ変えてあります。
バリエーション2:音形を対比させる
音形というのは、音が「上がって、上がって、下がって」みたいな上下する形のことです。
先ほどのサンプルを2回繰り返すとして、1回目と2回目で音形を変えて対比させてみます。
1小節目の下がっていたところを上げて、4小節目の上がっていたところを下げてみました。
バリエーション3:前の小節から始める
楽器でも歌でもよくあるパターンです。
前の小節から始めることで疾走が出たりしますが、ゆったりな曲でも多用されます。
(コードは、最初にCが鳴ってからF⇒C⇒G⇒Cです)前のサンプルを一拍分前にズラしただけですが、印象が変わりましたね。
「どれくらい前から始めるか?」は自由です。
洋楽だと2小節前の途中から始まって「それってもう、前のパートの一部だよね?」って感じのも多かったりします。
また、コードを進行を聞きながら鼻歌でメロディーを作る場合、どうしても小節頭から始めがちになります。
前もって「ここは前の小節から始めよう」と決めておくと、自然に取り入れられます。
次の記事では、Bメロの作り方を解説しますね。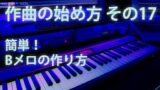
作曲の始め方 その17:簡単!Bメロの作り方
この記事では「作曲の始め方 その17」として、Bメロのメロディーの作り方を解説しています。
この記事のまとめ
↓の3つを意識すると、メロディー作りのバリエーションを増やせます。
- 2つの短いフレーズを繰り返す
- 音形を対比(上下逆)にしてみる
- 前の小節から始めてみる
次の記事では、Bメロの作り方を解説しますね。
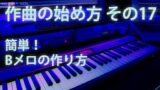
作曲の始め方 その17:簡単!Bメロの作り方
この記事では「作曲の始め方 その17」として、Bメロのメロディーの作り方を解説しています。