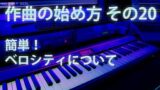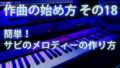この記事では、メロディーが先に出来た場合に、後からコードを付ける方法をご紹介しますね。
目次
メロディーへのコードの付け方 4ステップ+α

同じメロディーでも、コードが違うと印象が変わります。
そのため、メロディーへのコードの付け方は重要です。
でも、こんな事を書くのは気がひけますけど……。
メロディーへのコードの付け方に正解はありません。
自分が良いと思ったら、それが正解です。
とはいえ、ある程度の目安はあります。
1つずつ説明しますね。
ステップ1:1音目をコードトーンにしてみる
まずは、メロディーの最初の音をコードトーンにしてみます。
たとえば、キー=Cメジャーで、↓のようなメロディーだったとします。

(クリックで拡大)
最初の音がCから始まっています。
Cメジャーのダイアトニックコードの中で、コードトーンにCを含むのはC・F・Amの3つです。
そのため、C・F・Amの3つが候補になります。
ステップ2:コードトーンとノンコードトーンの割合
以前の記事でもご紹介しましたが、「メロディーのそれぞれの音がコードトーンか、ノンコードトーンか」の割合は大切です。
ジャンルや好みによりますが、「メロディーの6~8割がコードトーン」になるようなコードを選ぶと、バランスが良いです。
先ほどのメロディーとコードC・F・Amの関係を見てみます。
赤=コードトーン、黄色=ノンコードトーンです。
コードFだとノンコードトーンが多いので、候補はC・Amになります。
コードトーンとノンコードトーンの割合については、↓の記事でくわしく解説しています。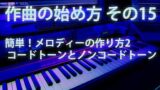
ステップ3:メジャーコードかマイナーコードか
同じメロディーでも、コードがメジャーかマイナーかで聞こえ方が変わります。
そこの部分を明るく感じさせたいならメジャーコード、暗く感じさせたいならマイナーコードを選びましょう。
↓の音源は、前半がCメジャー、後半がAmです。
ステップ4:コードの機能
最初の頃はあまり気にする必要はありません。
ひと通りコードを付けたあと、「んん~……なんかしっくり来ないな」と思ったら、
- 同じ機能を持つコードと入れ替えてみる(例:同じトニックであるIとVImを入れ替えてみる)
- 違う機能を持つコードと入れ替えてみる(例:トニックのIとドミナントのV7を入れ替えてみる)
ちなみに、パートの最後がIIImだとしっくり来ない場合が多いです。
IIImがしっくり来ない時は、他のコードと入れ替えてみましょう。
コードの機能については、以前の↓の記事で解説しています。

補足1:テンションコードやsus4など
テンションコードやsus4などのコードも、最初のうちはあまり気にしなくてOKです。
ただし、V7とツーファイブ(IIm7⇒V7、IIm7-5⇒V7)だけは、7thコードにするのを習慣づけておいた方が、のちのち楽です。
慣れて来たらadd9やsus4なども取り入れて、複雑な響きやコード進行を楽しみましょう。
補足2:ノンダイアトニックコード
メロディーにスケール外の音が含まれている場合は、借用和音・一時転調・セカンダリードミナント等を検討することもできます。
↓の記事でくわしく解説しています。
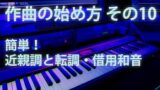

補足3:どうしてもしっくり来ない場合は?
どのコードを付けてもしっくり来ない場合は、「ここにはこのコードを使う!」と決めたうえで、コードに合わせてメロディーを変更しましょう。
次の記事では、打ち込みの際に重要な「ベロシティ」について解説しますね。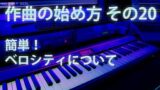
この記事のまとめ
先に作ったメロディーにコードを付ける際は、下記のことを意識しながら試行錯誤しましょう。
- メロディーの1音目がコードトーンになるようにする
- コードトーンとノンコードトーンの割合
- メジャーコードかマイナーコードか
- コードの機能
- (テンションコードやsus4などは、慣れてからでOK)
- (V7とツーファイブは7thコードにする)
- (メロディーにスケール外の音があるときは、ノンダイアトニックコードも検討できる)
- (どうしてもしっくり来るコードがない場合は、メロディーを変更する)
次の記事では、打ち込みの際に重要な「ベロシティ」について解説しますね。