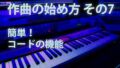この記事では、実際にコード進行を試す際に気をつけるべき「共通音保留」「ベースに反行」という原則について解説しますね。
実際にいろんなコード進行を試しましょう!その際の2つの注意点
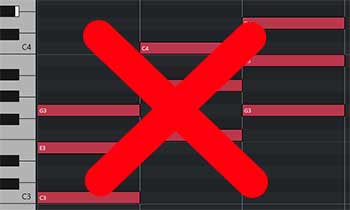
さていよいよ、実際に音を出して遊ぶ時間です。
基本となる3コードの進行(CFGC)を元に、各コードの機能(詳細は前の記事を参照)を思い出しながら、いろんな組み合わせを試してみましょう。
ただその前に、覚えておきたい2つの注意点があります。
2つとも厳密に守る必要はありませんが、「いつまでも初心者っぽさが抜けない人」にならないために必要な知識です。
(演奏者にとっての常識なので、作曲の話ではあまり話題にされません。そのため、楽器未経験の方はいつまでも身につかないままになりがちです)
1:共通音保留の原則
「コードが変わっても、共通する音がある場合は、そのまま弾こう」という原則です。
例として、コード進行CFGCのC⇒Fの部分に注目します。
構成音は
コードFの構成音:F A C
この際、↓の画像の左側のようにCEG・FACと弾くと、初心者っぽさの原因になります。

(クリックで拡大)
構成音Cが共通しているので、画像の右側のように、コードFの時の構成音Cは、コードCの時の構成音Cと同じところを弾きます。
聞き比べてみましょう。
2:ベースに反行の原則
「1」では共通音がありましたが、次は共通音がない場合です。
ピアノを例にすると、左手で低い音を弾き、右手で高い音を弾きます。
その際、左手で弾くrootのことをベースといいます。(楽器のベースとは無関係で、低音のことです)
また、右手で弾く一番高い音をトップノートといいます。
そして、「ベースが上がるときはトップノートを下げる、ベースが下がるときはトップノートを上げる」をベースに反行の原則といいます。
コードF⇒Gと進行する場合を見てみます。
F⇒Gはベースが上がっているので、GのトップノートDを1オクターブ下に持って行きます。
聞き比べてみましょう。
たくさん試してみましょう
2つの原則を気にしながら、CFGCを元にいろんなコード進行を鳴らしてみましょう。
急に「たくさん試そう」なんて言われても困るでしょうから、目安をご紹介しておきます。
ただし下記の目安にこだわる必要はなく、「自分がどう感じるか?聞こえるか?」を大切にしましょう。
- TはSD・Dどちらにも自然に進める
- DはTに進みたがる
- D⇒SDはしっくり来ない場合もある
- SDはDに進みたがるけど、Tにも自然に進める
- 始まりはTが基本だけど、SDやDでもOK
- 一段落する部分では、Tで終わるのが一般的
- サビ前など、「緊迫感のあるDで終わってサビヘ」みたいなのもアリ
- SDで終わると独特の雰囲気
- VIm⇒IV⇒I⇒V
- I⇒VIm⇒II⇒V
- I⇒V⇒VIm⇒IIIm
- IV⇒VIm⇒IIm⇒I
もちろん、「1小節ごとに1コード」とか「絶対4つに区切らないといけない」みたいなルールはありません。
1小節内で2つや3つにわけてもいいですし、同じコードが2小節続いてもOKですし、「8小節で1パターン」なんかもOKです。
(コロコロ変えすぎはしっくり来ませんけど)
また、VだけはV7にするのが一般的です。
理由は省略しますが、V(D)⇒I(T)よりもV7(D)⇒I(T)の方が終止感が強くなります。
マイナーキーのコード進行
マイナーキーの場合も、Im・IVm・Vmが基本になります。
ただしマイナーキーの場合、Im・IVm・V7とする場合が多いです。
Vmだと終止感がほとんどないからです。
VmをV7に変えれば、メジャーキーの時と同じような終止感があります。
次の記事では、ツーファイブという進行について解説しますね。

この記事のまとめ
- コードが変わった時、共通の音がある場合は、そのまま同じ高さの音を鳴らす
- ベースが上がっている時はトップノートを下げる、ベースが下がっているときはトップノートを上げる
- VはV7にすることが多い(終止感が強くなる)
- マイナーキーの場合もVmはV7にすることが多い
次の記事では、ツーファイブという進行について解説しますね。