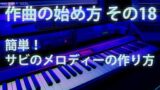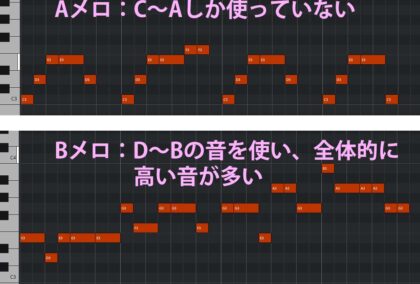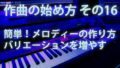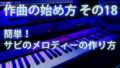この記事では、Bメロの作り方を解説しますね。
Bメロを作る際の4つの要素

音楽にもよりますが、曲を構成するパートは、
- イントロ
- Aメロ
- Bメロ
- サビ
- 間奏
- (プラスα)
これまでの記事で作ったメロディーをAメロとすると、次はBメロになります。
Aメロのことをまったく考えずにBメロを作ると、無関係なパーツを組み合わせただけのチグハグな印象になります。
Bメロを作る際は、次の5つに気をつけます。
- メロディーの単位を変える
- メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える
- メロディーの音形を変える
- 音域を変える
- コード進行を変える
1:メロディーの単位を変える
たとえばAメロが1小節のフレーズの繰り返しだった場合、Bメロは2小節や4小節のフレーズの繰り返しにすると、Aメロとの差別化ができます。
(もちろん、逆のパターンでAメロ2小節⇒Bメロ1小節もOKです)
↓の音源は、Aメロは「1小節のフレーズx4」が元になっているので、Bメロは「2小節のフレーズx2」にしてみた例です。
(コード進行はAメロ=C⇒F⇒G⇒C、Bメロ=Am⇒F⇒C⇒Gです)
(クリックで拡大)
※Bメロの前半・後半のアレンジについては、前記事の「メロディー作りのバリエーション1・2」をご確認ください。
2:メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える
Aメロが8分音符中心なので、4分音符中心に変えてみた例です。
3:メロディーの音形を変える
Aメロが「上がって下がる」という音形なので、Bメロは「下がって上がる」にしてみた例です。
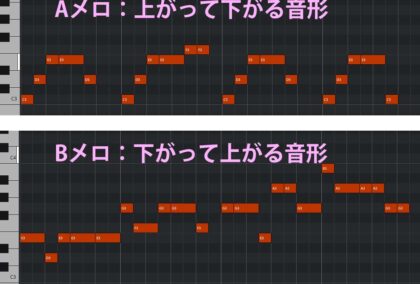
(クリックで拡大)
4:音域を変える
先ほどの「3」と同じ例です。
AメロはC~Aの音域に収まっていて、全体的に低い音が多いです。
一方、BメロはD~Bの音域で、全体的に高い音が多くなっています。
5:コード進行を変える
ここまででご紹介したサンプルはすべて、Aメロ=C⇒F⇒G⇒C、Bメロ=Am⇒F⇒C⇒Gです。
Bメロの次にサビが来る場合は、Bメロの最後をV(今回の例ではG)にすると、盛り上がった感じでサビにスムーズにつながりやすいです。
また、主に洋楽などは、「曲の間ずっと同じコード進行」というケースも多いです。
コード進行に凝れば凝るほど、「日本っぽいなぁ」という雰囲気になりがちです。
次の記事では、いよいよサビの作り方を解説しますね。
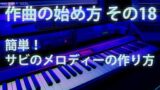
この記事のまとめ
Aメロのことをまったく考えずにBメロを作ると、「無関係なパーツを組み合わせただけ」になって、全体的にチグハグな印象になりやすいです。
そのため、Bメロを作る際は、↓の5つに気をつけましょう。
- メロディーの単位を変える
- メロディーのリズム(1音1音の長さ)を変える
- メロディーの音形を変える
- 音域を変える
- コード進行を変える
また、Bメロのコード進行の最後はV(5度)にすると、盛り上がった感じでサビにスムーズにつながりやすいです。
次の記事では、いよいよサビの作り方を解説しますね。